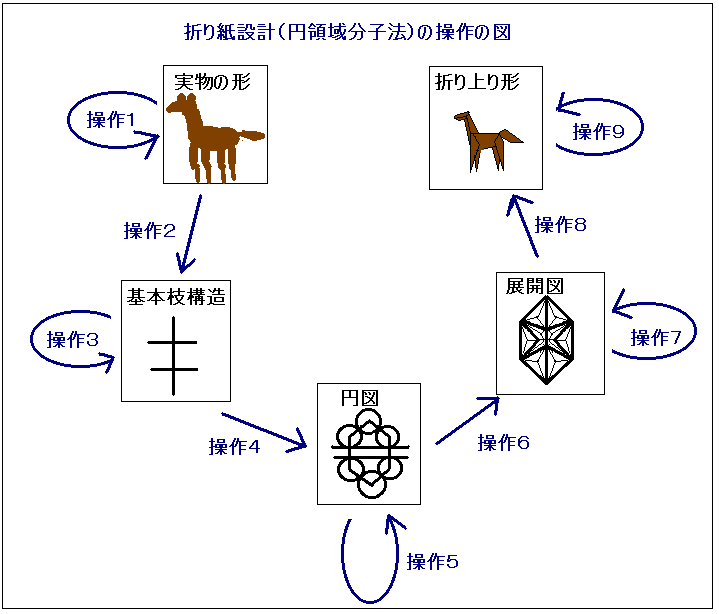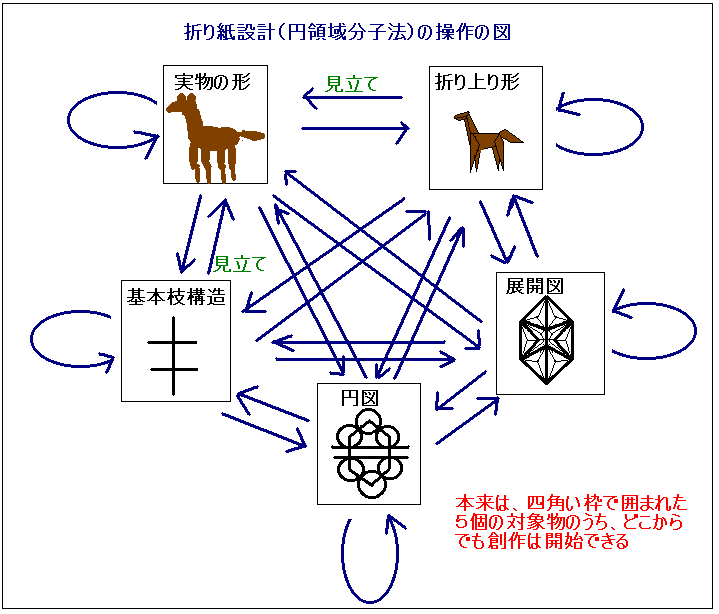ここをクリックすると、メインページに戻ります。
===============================================================================
=====第12話 創作の手順をまとめてみよう======
いままで、箇条書き的に色々な話題を書いてきましたが、だんだんごちゃごちゃしてきました。
創作全体における一連の操作を初めから終わりまで流れ図にまとめておくと、色々な
技術をまとめるのに便利かもしれません。
というわけで、今回は折紙設計法の流れ図を見渡してみましょう。
もちろん、創作にこうしなくてはいけないなどという決まり事はないので、ここで取りあげる
流れ図も、ほんの一例にすぎませんが、なるべくわかり易い円領域分子法の流れ図を
扱いますので、参考にしていただければ幸いです。
例として、円領域分子法で馬を設計することを考えましょう。
設計の開始から完成まで5つの対象物があると考えられます。それは、
(A)実物の形
(B)基本枝構造
(C)円図
(D)展開図
(E)折り上り形
の5つで、設計はこれらの対象物を順々に変形していくことに他なりません。
その変形操作は細かく見ると9個の連続操作から成り立っています。それは、
(1)(AからAへの変形操作) 実物の形の変形
(2)(AからBへの変形操作) 実物の形から基本枝構造への変形
(3)(BからBへの変形操作) 基本枝構造の変形
(4)(BからCへの変形操作) 基本枝構造から円図への変形
(5)(CからCへの変形操作) 円図の変形
(6)(CからDへの変形操作) 円図から展開図への変形
(7)(DからDへの変形操作) 展開図の変形
(8)(DからEへの変形操作) 展開図から折り上り形への変形
(9)(EからEへの変形操作) 折り上り形の変形
図にすると下のような感じです。
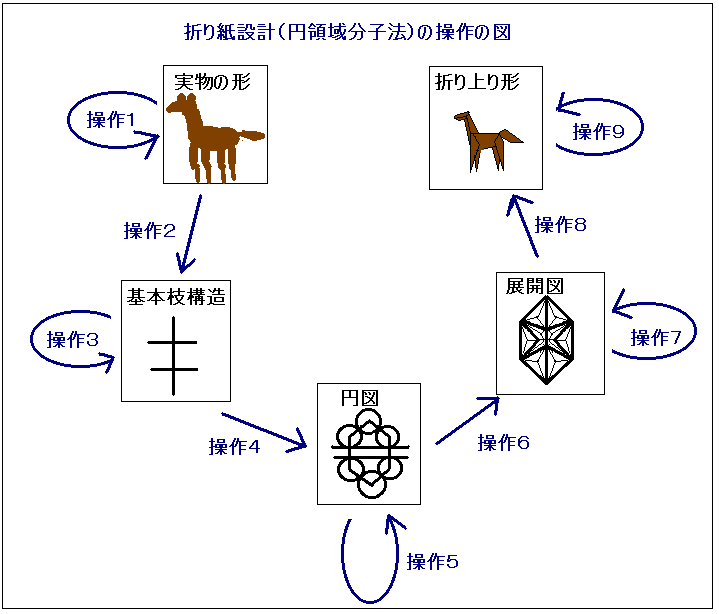
もし折紙設計が良くわからないという人がいたら、この図を見て、どこでつまずいて
いるか確認してください。
なお、より、現実的には設計手順は下図のようになるはずですが、
下図については混乱を避けるため、別の項で扱います。
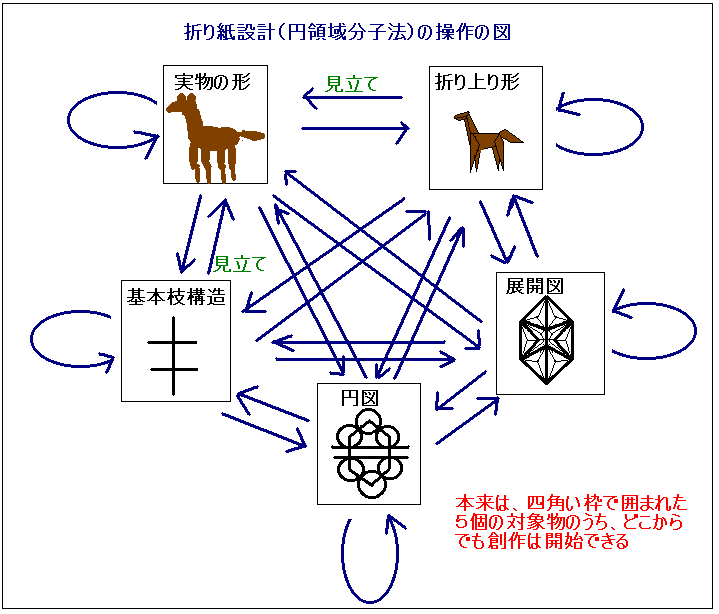
この項続きます
************************************************************************
ここをクリックすると、メインページに戻ります。