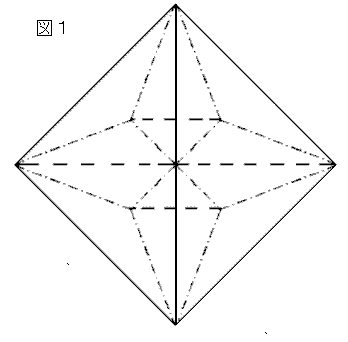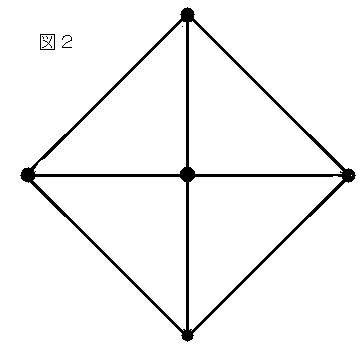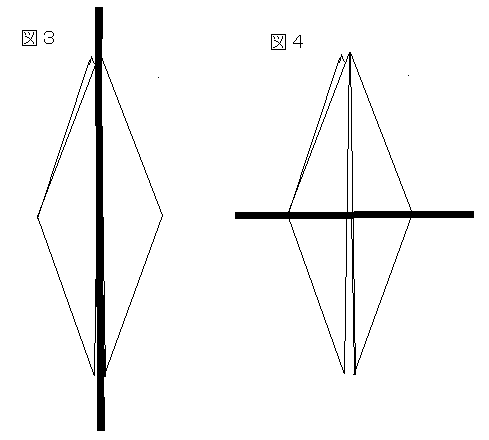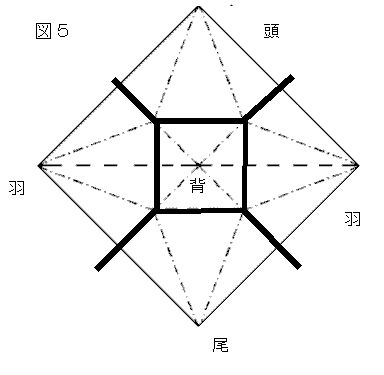ここをクリックすると、メインページに戻ります。
===============================================================================
=====第6話 縦分子と横分子をいっしょにしてみる======
まあまあ、なにはさていき「つる」の展開図を眺めて見ましょう。
つるの展開図では4つの直角二等辺三角形分子が対称性よく配置されていますね。
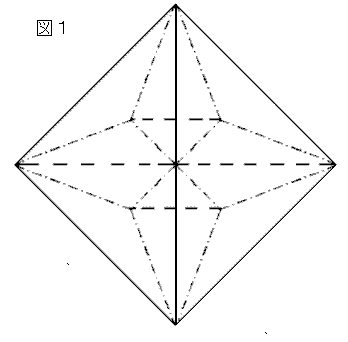
さて、この展開図を折ったらどんな形になるかを考えましょう。はいそうです。
つるの基本形になるに決まっていますよね。それはそうなんですけど、展開図のどの部分が
つるの基本形のどの部分に対応するかを知りたいわけなんです。それにはまず「つるの基本形」
がどんな形かを知っている必要があります。わかりきったことのような気がしますが
一応確認しますと、つるの基本形には大きなカドが4つあります。そのうちの一つは頭に、
もう一つは尾に、残りの2つは左右の羽になるわけです。さらに小さいカドが一個ありますね。
なになに、そんなのどこにあるのかですって、ここです、つるの背中になる小さな
三角形の部分もカドと見なしましょう。さて、展開図のどこが「つるの基本形」の
どの部分に対応するかを想像しましょう。どうでしょう。どうするといいかというと、
一つの方法としては折紙分子の境界線だけに注目するといいのです。だから、極端なことを言うと
図1のつるの基本形は紙で出来ているのではなく、図2のように、分子の境界線だけが針金でできていて、
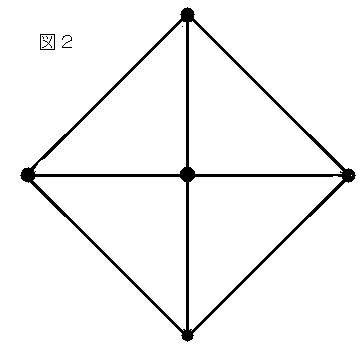
あとはなにもないと考えてもいいのです。針金と針金が交差している点は溶接されていて
離れないけれど、曲げることはできるものと考えてください。これをカキカキ折り曲げて
一直線状にしたときにどんな形になるかを想像すればよいのです。これが、縦分子から
出来上がり図を想像する一つの方法です。
ところで次のようなことを考えた方はいませか?「分子を組み合わせて設計をすると聞いたら、
たとえば頭の部分の分子、羽の部分の分子、尾の部分の分子、背中の部分の分子を
組み合わせて展開図ができると想像するでしょうに、全然そうなってないじゃないの、
これじゃあちょっとわかりにくいなあ」と。うーむ、そういえばそうですねー。
縦分子から出来上がりを想像するのは慣れれば勘でわかるのですが、最初は戸惑われる
かもしれません。だけど、もしお望みでしたら、頭の部分の分子、羽の部分の分子、
尾の部分の分子、背中の部分の分子を組み合わせて展開図をつくる方法もちゃんとあるんですよ。
ちょっとそれを考えてみましょう。つるの基本形を縦の一値分子で分解しましたが、
それは図3のように縦方向の線で基本形を分解したことになるのです。一つ一つのカドを
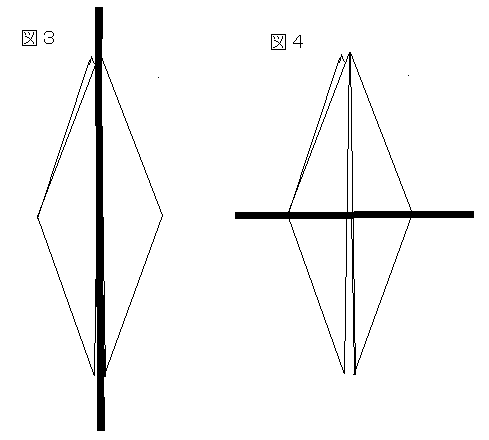
壊さずに分解するには、本当は図4のように横方向の線で分解しなくてはならないんです。
え、なんでそうなるのかですって。それは、実際につるの基本形を2個折って
一つは図3の縦線で、もう一つは図4の横線で切り分けてみればすぐ納得していただける
と思いますので、できれば実際にお試しください。つるの基本形を図4に対応する方法で
一値分子に分解すると図5のようになります。どうでしょう、このように横境界線性一値分子を
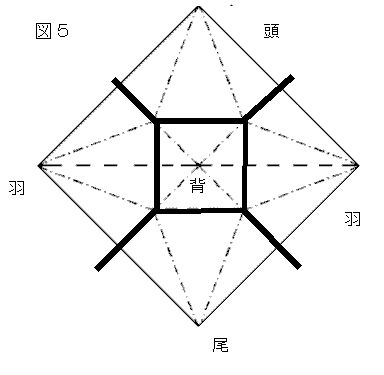
用いると、頭の部分の分子1個、羽の部分の分子2個、尾の部分の分子1個、背中の部分の
分子1個、というぐあいに、展開図上の分子と、実際に折った基本形でのカドがきれいに
対応しているではありませんか。このように、横境界線性一値分子系は、折ってみた時の
基本形のカドとの対応が一対一のなっていてわかりやすいのです。一方、縦境界線性一値分子系は、
折ってみた時の形との対応はつけにくいのですが、展開図上の扱いは楽なのです。
さあ困りました。いったいどっちの分子系を用いればよいのでしょう。って全然困りませんね。
両方を同時に用いればよいのです。さて、こうして縦境界線性一値分子系と横境界線性一値分子系を
同時に考えると都合のよいことがあります。それはなにかというと、分子の境界線を縦方向と
横方向の2つの方向軸で捕らえているのですから、つまり、対象とする分子を2次元の面として
捕らえていることになるのです。設計者は折ろうとする形を、形を面としても、
奥行きのある立体としてもとらえているわけですから、それを設計に生かすためには
縦と横の2方向の分子系を用いれば設計の段階から面としての広がりをとりいれられるのです。
えっ、なになに、こういうことを応用すればきっと素晴らしい設計作品ができるのだろうですって。
うーん、痛いところをついてきますねー。設計は理論を優先させても上手くいくとは
かぎらないのですよねー、っていうか、良い作品を作るためには、設計法は基本的な
ところだけを確実に押えておけばよくって、あとは各人の造形センスとか情熱とかの方が
よっぽど重要ってことも普通ですから。えっ、じゃあ何でわざわざ縦とか横とか
考えるのかですって。うーん、まあ、たまには新しいアプローチによって、新規の作品群が
できる場合もありますし、これはうまくいくとかなり嬉しいわけです。それにやっぱり
縦分子と横分子を使い分けられれば、どんな形でもとりあえずは折るということが、
確実にできますから気分的に楽ということも結構大きいかとおもいます。
************************************************************************
ここをクリックすると、メインページに戻ります。